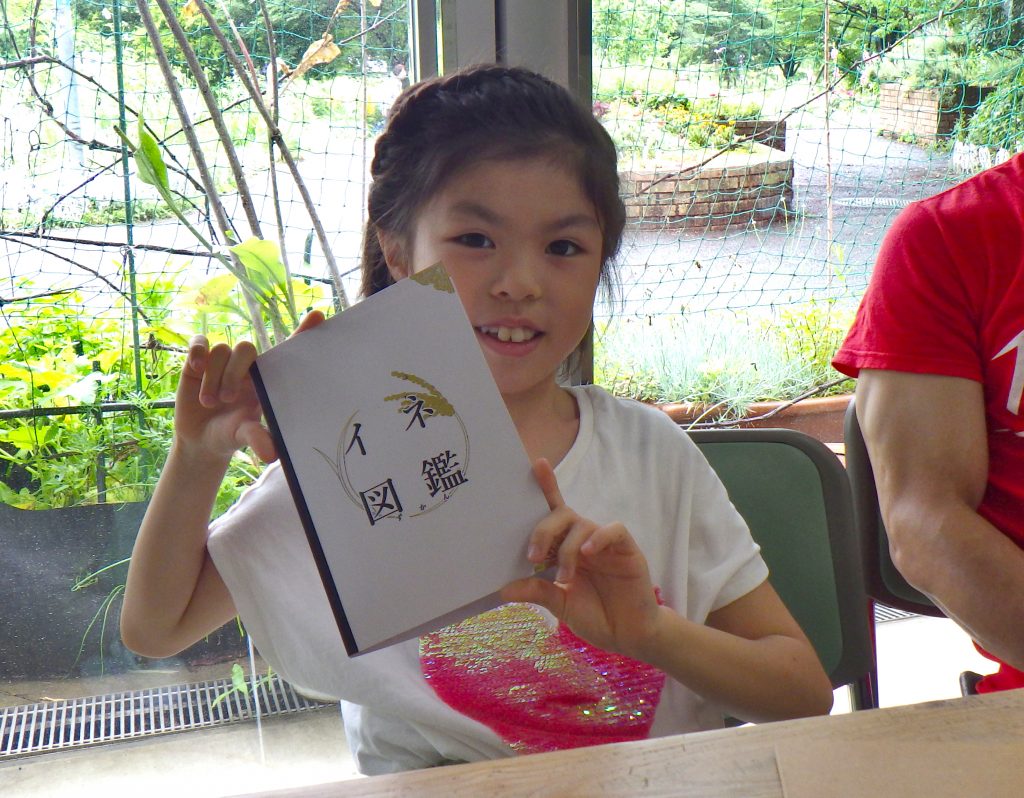みなさんこんにちは!
学習館スタッフのすぅーちゃんです。
今回は7月12日に開催した
イベント「こうえんのヒーローになろう」の様子をご紹介します!
この日は夏らしい暑い日でしたが、4人のヒーローが集まってくれました。
まずは、マントをつけて、ヒーローに変身!

みんなで公園に落ちているゴミを拾います!
残念なことに、利用者の中にはゴミを捨ててしまう人がいるんです・・・(泣)
みんなが公園で気持ちやすく過ごせるように、
ヒーローが助けてくれました!!

ありがとうヒーロー!!
次は雑草抜きをします。
たくさん緑があるけれど、雑草も増えて困っています・・・。
ヒーローは公園の植物も守ってくれます!

ありがとうヒーロー!!!
助けてくれたヒーロー達には、
ヒーローシールをプレゼントしました♪

公園を楽しむみんなのために頑張ってくれた
ヒーローありがとう!!!
これからも素敵な公園を大切にしてくれると嬉しいです♪